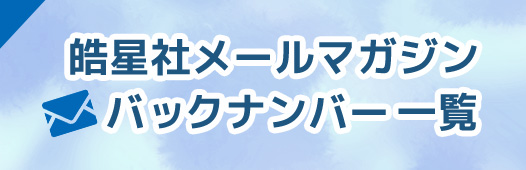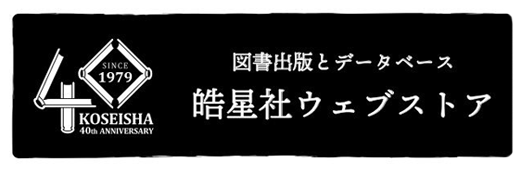稲葉上道君の「今、国立ハンセン病資料館で何が起きているのか」(『歴史地理教育』2021年1月919号)を読む
文責 皓星社・藤巻修一
初めに
私たちは一九七九年の創業以来、ハンセン病患者、元患者さんたちの作品集の出版を手がけ、二〇〇三年から二〇一〇年にかけてはその集大成として『ハンセン病文学全集』(全一〇巻)を刊行しました。この企画がスタートしたのは一九八〇年代の中頃で、その頃は、ハンセン病資料館もなく、したがってハンセン病資料館の創設、稲葉君の入館のいきさつとそれ以降の活動(勤務ぶり)を一部始終見てきました。
今回、遅ればせながら稲葉上道君の「今、国立ハンセン病資料館で何が起きているのか」(『歴史地理教育』2021年1月919号)を読むことができました。今まで、稲葉君の支援者たちの文章を読んでそれが的外れであることを指摘してきましたが、今回本人の主張を読むことで稲葉君の口から問題の所在をより明確にできたから皮肉なことです。
稲葉君は、記事の「はじめに」で「ここ数年、資料館の価値を変質させる動きと、それに抵抗する者への攻撃が続いている」といいます。この大仰な「価値を変質させる動き」とは一体何でしょうか。
ハンセン病資料館の「理念」と博物館の「機能」
稲葉君は本稿の「1 国立ハンセン病資料館の価値」で「資料館の歴史を概観したい」としてその歴史を述べていますが、資料館の歴史は稲葉君の独占するものではなく等しく共有するものですからここは触れません(ただ、稲葉君の記述には細部に意図的と思える誤りがありますが、本題を外れるのでここでは取り上げないことにします)。
次に「2 崩壊の過程」として、二〇一六年度から日本財団が資料館の管理者になったことによって「崩壊」が始まったといいます。一体何が「崩壊」したのでしょうか。
これを検証する前に確認しておきたいことがあります。
それは、資料館の「あり方」という時、二つの側面があるということです。一つはその資料館の成り立ちや意義や目的をめぐる「理念」というべきものであってこれは個々の施設によって独自なものがあり、ハンセン病資料館にも譲れないものがあるはずです。
もう一つは、どの博物館にも共通の「機能」とでも言うべきものであって、国際博物館会議(ICOM)の現行の定義によれば「博物館とは、社会とその発展に貢献するため、有形、無形の人類の遺産とその環境を、教育、研究、楽しみを目的として収集、保存、調査研究、普及、展示する公衆に開かれた非営利の常設機関である」と定義され、どの博物館学の教科書も同様の記述があります。
稲葉君の主張はハンセン病資料館が「対外的なアピールと入館者数獲得に偏った方向性を打ち出し、資料館本来の目的から逸脱したものに活動方針を変えた」ということです。稲葉君はこれに「反対」し「抵抗」したといいます。しかし、このどこが「本来の目的から逸脱した」「資料館の価値を変質させる動き」なのでしょうか。稲葉君の文章のどこを読んでもこれについては説明がありません。資料館の「機能」からしたら「対外的なアピールと入館者数獲得」活動は「本来の目的」そのものです。いくら立派な展示や企画でも来館者がいなくては意味がありません。今更これに注力するというのは、従来この活動がなされていなかったからにほかなりません。
稲葉君のこの記述には資料館の日常活動の改革を、本来の目的や理念を変質させる動きであるかのように誘導しようとする意図が見え隠れしています。
根拠のない主張
議論の筋を追って「3 エスカレートする人権侵害」は、あとで検討することとして「4 問題の起源」を読んでみます。
この「問題の起源」は稲葉君の従来の主張にはなく、兵庫解放教育研究会の『むらぎも通信』(2020年10月25日発行 315号)の栗山和久氏の「入札制度という隠れ蓑を利用し、運営受託者を国の意向に沿う団体に変更し資料館の在り方や理念をねじ曲げ、在園者自身から国主導へと転換、そのためには稲葉氏らを資料館に置くわけには行かなかったのではないか」という古い活動家のテンプレートに稲葉問題を当てはめたものをなぞったものです。栗山氏の主張は、文末が「ではないか」という疑問形なのがむしろ正直な、根拠のない「陰謀論」(この批判は別に書きました)にすぎません。
https://www.libro-koseisha.co.jp/info/20201207/
本稿の稲葉君の主張によれば、ハンセン病資料館が国立に移管された時点で「厚労省は新しい常設展示の内容に介入し、当時の受託者も、入所者よりも厚労省の意向を優先し、我が物顔に資料館の方向性を変えようとした。国立の施設と言いながら、法令による設置規定がなかったから(今もない)ため、国と受託者が資料館を好き勝手にできる余地が生まれてしまったのである」、あるいは「単年度の民間委託の繰り返」し、「国立」に館名変更したことで「厚労省や受託者は、資料館が国の意向に沿う施設に生まれ変わったかのような態度を取った」といいます。そしてそれは今日まで続いているということです。
ちなみに稲葉君とともに「追放」になったというK学芸部長は「国立館になったことで『国寄りの展示になっているのではないか』というような誤解をする人も出てきて、若い学芸員が苦しんでいた」と証言していて稲葉君の「主張」は「誤解」だと述べています。
https://leprosy.jp/people/kuroo/
ところで国立移管時点の最古参の学芸員は稲葉君でした。もし、当時からそのような認識と問題意識を持っていたのならなぜこの時点でそれを指摘し「抵抗」をしなかったのでしょうか。しかし、当時そのような動きは一切ありませんでした。
一方、「国に責任を持たせる」ために国立移管を主張した統一交渉団(ハンセン病国賠訴訟の原告団、弁護団、遅れて参加の全療協の三者。のちに家族訴訟の原告団も加わり四者)は手放しで国立移管を求めたわけではありません。ハンセン病資料館の理念や展示の改変などを国や管理受託団体が勝手にできるものではなく、資料館の運営や展示は、全療協、原告団、弁護団の代表に学識経験者を加えた資料館の「資料館等運営企画検討会」「展示見直し検討会」などの検討の上でおこない、現場の運営は「運営委員会」が担うよう幾重にも担保されています。前二者の「検討会」は、運営受託側はメンバーの要請に応じて現状を説明する立場で出席しますが「検討会メンバー」ではありません。稲葉君はこの点については一切触れず、国や運営受託者が恣意的に運営方針を変更できるかのように言います。しかし、国や運営側が資料館のあり方や運営をほしいままにしたり、運営に横槍を入れるならば、統一交渉団や各委員会が当然問題にするのであって、一学芸員の「抵抗」に任せて看過するわけはないのです。
このような問題に一学芸員である稲葉君の介在する余地はなく(その意味で栗山氏の上記の「ストーリー」も破綻しています)、問題の所在は別なところにあるのです。
存在しない「重大な問題」
統一交渉団は資料館の「理念」や「常設展示」に関心がむかい、資料館の日常的な「機能的側面」については現場の学芸員に任せきりとなっていました。ここに稲葉君が勝手気ままに振舞う余地が生じました。稲葉君自体が当時の自身の採用の次第を「ハンセン病のことなど、まったく知らない状態」で「大学院で修士二年が終わるときに就職先も決まっていない、修士論文も書けていない、これは三年目に突入するのは確実、という状況になりまして、これはどうしたものかと思っていた」時に「採用も公募などといった段取りはまったくなくて、『学芸員資格持っていて働きたい人がいたら、とにかく連れてきて』みたいな感じだったようです」と述べている通りです。
https://against2020hansens-issues.info/archives/434
さらに、後に学芸部長になるK氏についても、専門はハンセン病とは全く関係のない考古学でしたが当時の館長が「そんなことをやってぶらぶらしているんだったら、ウチの館に来て手伝え」と言って採用したと自ら語っています。
https://leprosy.jp/people/kuroo/
このように、学芸員の採用がまことに軽率であって、初めて学芸員を雇用するときに計画的に新人とベテランをバランスよく採用すべきところ、無計画に新人ばかりを採用してしまいました。現在の問題の遠因はそこにもありますから当時採用に関与した人たちの責任は重いといえます。
こうして稲葉君は先任で年長であるところから終始リーダーとしてふるまうようになりました。指導すべき先輩学芸員もなく、他の資料館との交流もなく孤立した資料館はガラパゴス化ししていきました。収集、寄託された資料は収蔵庫に入れっぱなしで学芸員の基本的業務というべき所蔵目録も作らず、長く『研究紀要』の刊行もなく、啓発活動もなく、何をしているかわからないのが実情でした。しかし、最古参の学芸員ということで学芸課長になりその独断的傾向はさらに顕著となっていきます。
その後、学芸員の増員に伴い経験も豊富でスキルも志も高い学芸員が採用になり徐々に稲葉君の頑迷で独断的運営に対する批判と改革の機運が盛り上がって行きました。二〇一六年に日本財団が運営管理者になった時には既に改革の萌芽は芽生えていて変化は運営委託団体の交代を機に起こったわけではありません。しかし、この改革の動きに日本財団側はそれまでの受託団体と違い理解を示しました。
「2 崩壊の過程」を読むと、二〇一六年度から日本財団に運営が変わったことで、入所者の「語り部」、館長からのパワハラが始まったといいます。「嘘を吹き込」んで「九〇歳になるその入所者(資料館創設の立役者で『語り部』)」の「怒りを煽り」、館長を「操る」日本財団職員がいたためだといいます。しかし、館長や語り部のH氏と最古参の学芸員である稲葉君は、十数年以上ともに働き深い信頼関係にあったのではないのでしょうか。代わったばかりの日本財団職員の根拠のない讒言を、館長や「語り部」のH氏がそんなに易々と受け入れるものでしょうか。また、稲葉君と同期採用の学芸員も改革の動きに同調して、稲葉君の「抵抗」に与してはいません(これら同僚学芸員を稲葉君は文中二度にわたって「私欲のために便乗した」と貶めています)。
二〇一八年三月資料館の機構改革によってあくまで「抵抗」を続ける学芸部長、学芸課長は異動になりました。すなわち、「2 崩壊の過程」というのは「稲葉体制」の崩壊の過程であり、稲葉君の頑迷で独善的なきわめて個人的資質に由来する問題なのです。したがって、本来ならば資料館の現場で「労働者」同士で話し合って解決するのが最善ですが、同僚たちによる職場改革の動きを頑なに拒否し、上長による「改善指導」をパワハラとして徹底的に「抵抗」する職員が改善の見込みがないと判断されたのはやむを得ないことではないでしょうか。運営に支障が生じる以上、これを放置することは人事権を持つ運営管理者の責任放棄とのそしりは免れません。これが「稲葉問題」の本質です。
したがってそれ以後の動きは、本質をくらます工作と言わなければなりません。「状況を見かねた私たち三人の学芸員は、二〇一九年九月労働組合を結成した」という組合結成自体が自己保身のための付け焼刃で、マスコミや運動家好みの「管理者対労働者」という図式を作るために「労働組合」を巧みに利用したのです。組合のツイッターのプロフィールによれば「国立ハンセン病資料館/重監房資料館/社会交流会館が、患者・回復者の主体性と尊厳を重視し、意向を尊重し、それぞれの館の設立目的や役割を堅持し、ひいては社会にとって有意義な博物館施設であり続けるために労働組合を結成」したといいます。文字通りならば我々も反対する理由はありません。しかし、そのような正当な問題意識のもとに準備を重ねた組合結成ならば、広く学芸員・職員の理解を得て立ち上げるべきで、そうした準備を欠いた急ごしらえであることは上部団体がハンセン病療養所の組合など関連団体の加入する全医労ではなく、加盟の容易な国公一般(「国公労連」とは別)であることでも裏付けられます。
当初は単純なパワハラ、ネグレクトに対抗しての組合結成といいながら、その後の「学習」の結果、「無期転換逃れ」とか『むらぎも通信』の出た二〇二〇年暮れ以降は背景に「国の策動」があるかのような主張が次々と加わってきました。すなわち、現場の上長・同僚との軋轢を、労働者の権利を守ろうとする「学芸員対日本財団」、ついで資料館の理念を守ろうとする「学芸員対政府・国」と構図を広げてきたのがこの間のいきさつです。
続く「5 資料館の価値を取り戻すために」の項では全くの後付けの空疎な記述が続きますがこの問題を検討するためには意味がないので略します。
品のない人格攻撃
最後に「3 エスカレートする人権侵害行為」に戻ることにします。ここでは無期転換ルール逃れのために五年目に日本財団から笹川保健財団に管理者を変えた「脱法行為」と、「活発に活動していた労働組合を破壊するために」稲葉君を排除したのが人権侵害だというのです。しかし、労働契約法の改正で無期転換ルールができたのは、二〇一三年のことでこの時の受託者は科学技術振興財団でした。なぜこの時、権利の行使をしなかったのでしょうか。この時にはこの制度は全く眼中になかったのです。
さらに、賛否両論あるこの問題(療養所内にも稲葉君への批判者は多い)で、コロナ禍で立ち入り制限中の療養所に「支援者」とともに入り込んで署名やカンパを要請し分断の種を持ち込み、同僚学芸員の反論文書を「事実の歪曲と捏造で私たちの名誉を毀損する」と根拠のない決めつけを行い、「私たちのことをほとんど知らないはずの外部の人間がSNS上で頻繁かつ執拗に攻撃するようになった」といいます。さらに「外部の人間は、同じものに雇われているかの如く、明確な役割分担と迅速な情報入手を持って、私たちを攻撃」しているといいます。明らかに筆者などはそのうちの一人でしょうが、主体的な判断で実名も所属も明らかにして、また全て公刊情報を根拠にした批判に対して「雇われているかの如く」というのは全く根拠を欠いた言いがかりでしかありません。
この項は「今、国立ハンセン病資料館で何が起きているのか」の中で最も残念な項目と言わなくてはなりません。「労働環境改善」のために組合を結成し、国の理不尽な圧力に抵抗したと主張する稲葉君がこのような品性を欠く攻撃をするのは、同僚に対して再三「私欲のために」という人格攻撃をするのと併せて理解に苦しみます。稲葉君の言動こそは言葉の正確な意味で「誹謗中傷」と言わざるを得ません。
また「私たち組合員三人を監視カメラで監視し」といいますが、「監視カメラ」といえば監視員が二四時間ディスプレイの前で目を凝らしているような陰湿なイメージを与えますが、これはどこにでもある「防犯カメラ」であって個人を特定して記録するものではなく、何かあれば再生・確認するのは通常業務ではないでしょうか。
終わりに
では、稲葉君の主張する「抵抗」を排して「資料館の価値を変質させる動き」の結果、資料館の現状はどうなっているのでしょうか。
稲葉君の言う「ここ数年」資料館の活動は目に見えて活発化しています。一例を挙げれば、二〇一五年から始まった出張講座は学芸員各自の持ち味を生かして学校や職場の研修として好評で、ホームページによれば二〇二〇年までに四七八回を数え参加者は述べ五六万九〇六〇人にのぼります。また、二〇二二年八月まで開催されていた企画展「生活のデザイン」展は、若者の参加者が目立ち会期延長のリクエストが多数寄せられたほど好評でした。この企画展は、無名の入所者が日常生活に工夫を凝らした品々を体系化した、等身大の生活者に寄り添う姿勢と眼差しがなければできない、長年出版活動に携わってきた我々をして、出版ではできない博物館だからできた企画であると唸らせた企画でした。それは稲葉君の時代に収蔵庫に入れられたまま埃にまみれて放置されていた資料を再調査して目録を作成することで可能となったもので学芸員たちの地道な努力の結晶なのです。
これが「私欲のために」と貶められ、それへの「反論」も立場上封じられた学芸員が黙って出した答えなのです。
このように稲葉君が主導した一五年と直近の五年間のハンセン病資料館の活動を比較すれば、「今、ハンセン病資料館に何が起きているのか」は明らかです。ハンセン病資料館は「変質」したのでも「崩壊」したのでもなく、資料館の理念を踏まえて活動が画期的に活性化し、コロナ禍で入館制限をせざるを得ない中で来館者も劇的に増加したのであって、稲葉君が「何に抵抗」してきたのかを事実が雄弁に物語っています。稲葉君は復帰して「もとの正常な運営」と主張しますが、現在の活動を全否定して稲葉課長時代の閉鎖的かつ強圧的な運営に戻すというなら徹底的に反対せざるを得ません。
つけたし
国立ハンセン病資料館と各園の歴史館、交流会館等はそれぞれの主体性を生かしながら連帯して啓発活動にあたるべきではないかと思います。しかし稲葉君の保身のための策動は、療養所内に分断の種を持ち込んだのにとどまらず、各施設の連帯を阻害することになっているのは誠に残念なことだと思います。また、この問題を奇貨として自らの運動や主張に利用する動きもまた残念なことと言わなければなりません。関係団体の皆さんには、客観的な視点から冷静かつ賢明な判断を望みたいと思います。(2022年11月1日)