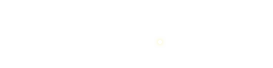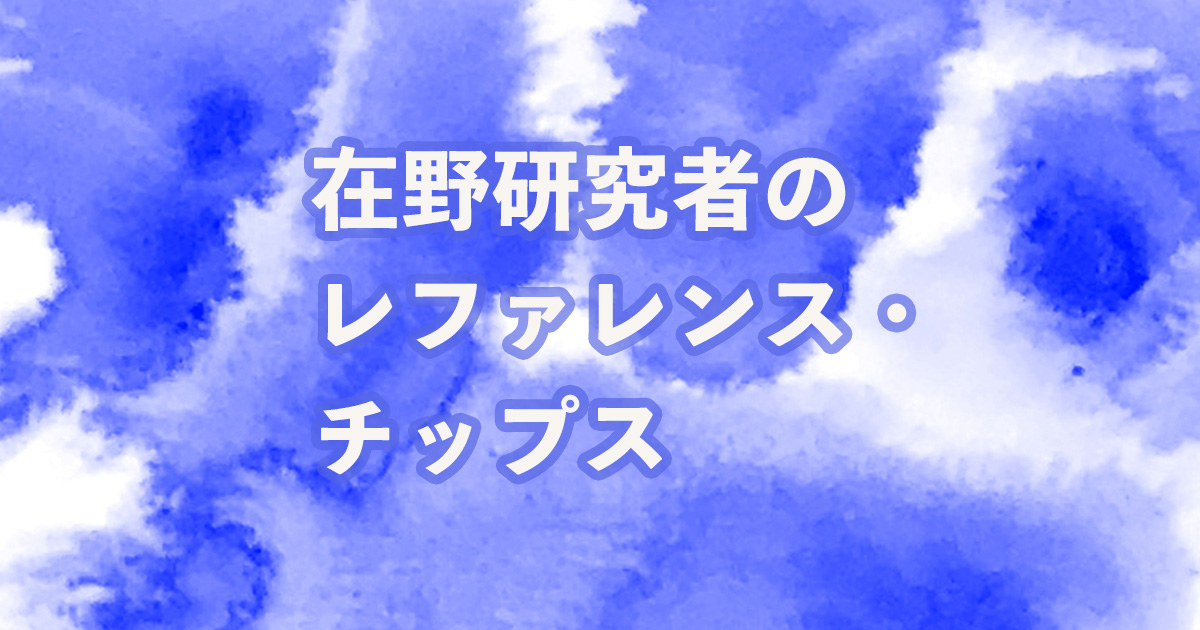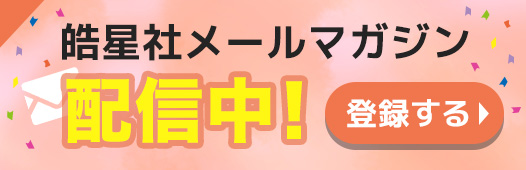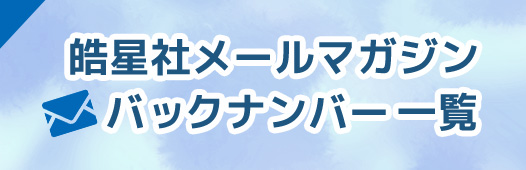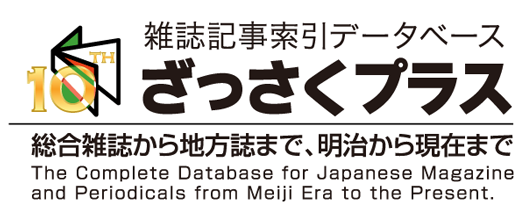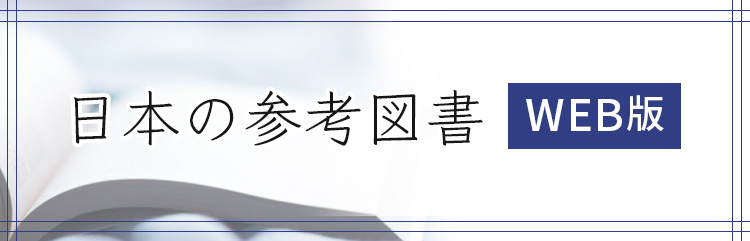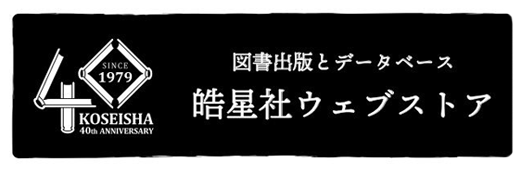Webコラム「 在野研究者のレファレンス・チップス 」一覧
- 第14回 天才魔術師と同じ魔法が使えるようになるために――「当たり前」を超えて
- 公開
小林昌樹(図書館情報学研究者) ■そんなの当たり前 前回、NDLサイトに秘蔵された「調べ方案内」を見つけるには、NDLがHP上に用意した独自分類を下りていって見つけたりせず、単にGoogleから直接「トピッ […]…続きを読む
- 第13回 パスファインダー(調べ方案内)の見つけ方
- 公開
小林昌樹(図書館情報学研究者) ■ある日の会話 「なんで日本の図書館ではレファレンス・サービスが広まらなかったんでしょう?」 「それは、サービスが目に見えないからさ。カタロガーの仕事は目録カードって形で残るからまだしも、 […]…続きを読む
- 第12回 自分の調べ物に最適の雑誌記事索引を選ぶには――記事索引の採録年代、得意ジャンルを知っておく
- 公開
小林昌樹(図書館情報学研究者) ■本は今、わりあいと見つかる むかしは読みたい本を見つけるのも一苦労だったが、現在では国会図書館(NDL)の全国書誌データがネット検索できるようになって、ひととおり探すことが […]…続きを読む
- 第11回 レファ協DBの読み方――事案を事例として読み替える
- 公開
小林昌樹(図書館情報学研究者) 1 はじめに ■うまく広まらなかったレファレンス業務 帝都東京が焦土と化して3年。アメリカから2人の一流図書館人――クラップさんとブラウンさん――がやってきて、国会図書館【図1】の業務をイ […]…続きを読む
- 第10回 索引の落とし穴を避ける――明治、大正、昭和期本の見出し排列
- 公開
小林昌樹(図書館情報学研究者) ■インデックスをちゃんと引けてる? 前職で他の図書館で調べたものを更に調べるという仕事があった。その際、他館や他課で調べたとリストにあるアイテム(レファ本)*でも、これは危な […]…続きを読む
- 第9回 次世代デジタルライブラリーの感想――日本語版Googleブックスの試み
- 公開
小林昌樹(図書館情報学研究者) ■はじめに 前回予告では「索引の排列」について取り上げるつもりだったが、なんとびっくりGoogleブックスもどきβ版を日本の国立国会図書館(NDL)が公開したので、ここに紹介したい。こうい […]…続きを読む
- 第8回 回答の手間ヒマを事前に予測する――日本語ドキュバースの三区分
- 公開
小林昌樹(図書館情報学研究者) ■主題と時間と空間と ベテランのレファレンス司書は質問を聞いた瞬間に――無意識的にせよ――答えがでるまでのコストや困難さを予測している。これは、経験的に察知できるようになるものだ。もちろん […]…続きを読む
- 第7回 答えから引く法――頼朝の刀の銘は?
- 公開
小林昌樹(図書館情報学研究者) 自分は西洋史出身のせいか、日本、それも前近代の歴史モノが苦手である。ただ、幸か不幸か、図書館のレファレンスでは、くずし字の読み解きなどは謝絶してよいことになっており、司書でいる限り古文書読 […]…続きを読む
- 第6回 「として法」――ツールのない調べ物にツールを用意する
- 公開
小林昌樹(図書館情報学研究者) ■1ジャンルあたり150冊のレファ本があるけれど 国会図書館のレファレンス室(館内的には専門室と言う)へ行くと体感できるが、いろんなジャンル、主題にいろんなレファ本がすでにある。 私がいた […]…続きを読む
- 第5回 明治期からの新聞記事を「合理的に」ざっと調べる方法
- 公開
小林昌樹(図書館情報学研究者) ■新聞紙*自体のこと 幕末明治から新聞紙が作られてきた。図書館にもそれらは備えられたのだが、通常、消耗品として廃棄され、帝国図書館ですら主要紙の保存に留まった。新聞紙の史料としての価値に気 […]…続きを読む