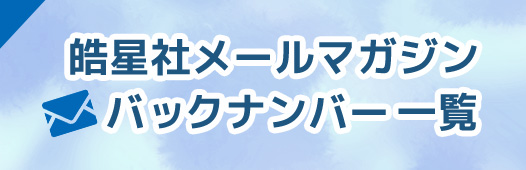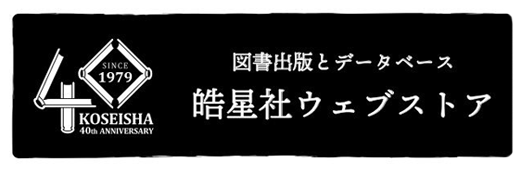大義なき全療協の宣言文-ハンセン病資料館の「不当解雇」問題はどこに行くのか?
大義なき全療協の宣言文
ハンセン病資料館の「不当解雇」問題はどこに行くのか?
2021年3月23日
皓星社 藤巻修一
【初めに】
知り合いの新聞記者や自治会筋からの複数の情報によると、3月に入って全療協は2月25日の臨時支部長会議の決定として関係各所に「国立ハンセン病資料館の館長問題に関する要請書(以下「要請書」という)」(会長名義)なるものと「宣言文(以下「宣言文」という)」(支部長会議名義)を送りつけているようだ。我々はその文書を入手したので若干「感想」を述べてみたい。本稿は「他組織」である全療協を批判することが目的ではなく、あくまで現・資料館の活動支持の文脈で読んでいただきたい。
【問題の経緯】
まず、不思議に思うのはなぜ全療協が強引な支部長会議の機関決定をしてまで執拗に他組織であるハンセン病資料館の館長人事に介入するのかという疑問である。
しかも、2017年の日本財団のホームページ〈Leprosy. jp〉の「People/ハンセン病に向き合う人々」のインタビューに藤崎陸安全療協事務局長は、全療協の課題は「入所者の人権問題と医師不足」と答えていて、この時点までは「ハンセン病資料館」には全く関心がないのである。
突然関心を示すのは2018年のハンセン病資料館の機構改革である。この時資料館は「黒尾和久学芸部長、稲葉上道学芸課長」制を廃して「事業部と管理部」に再編した。職掌が重なる学芸部、学芸課という組織より職掌を分担する改革後の組織の方が合理的に見える。「全療協ニュース」によれば黒尾和久学芸部長、稲葉上道学芸課長の職を解いたのが全療協の「主体性を損なう」という主張であって、すなわち全療協の言う「主体性を損なう」とは意に沿わぬ人事のことにほかならず、機構の改革自体が問題ではなく黒尾氏の処遇を問題にしたのである。
そして、「主体性」を保つために、すなわち資料館の人事を恣にするため、2019年には資料館の運営受託のための「法人組織」の設立を支部長会議の多数決で決定している。(ただし、この話には続報がない)また、2019年5月には支部長会議の決定として唐突に館長人事を問題にして館長の高齢を理由に退陣を要求している。現館長は就任時既に高齢で、終身の名誉職が暗黙の了解事項だった筈である。こういう場合「任期満了」まで見守るのが大人の態度ではないかとは以前書いたことである(「全療協ニュースを読んで」2020年9月)。2020年4月には運営団体が日本財団から笹川保健財団に変わったことを受けその運営を問題視している。
その場その場の思いつきで迷走していると言わざるを得ない。
一貫しているのは全療協の資料館への介入が「資料館運営の理念」でも「展示等への異論」でもなく全て黒尾和久氏への処遇に端を発した「人事問題」だということである。すなわち、他組織の人事の不満に端を発した横紙破りである。
ここに至る過程は2020年9月に「全療協ニュースを読んで」に詳述した。
「全療協ニュース」をよんで -この度のハンセン病資料館の元学芸員・稲葉上道氏たちの「不当解雇問題」に際して
そこを確認した上で、今回の「要請文」「宣言文」を読んでみた「感想」である。
【宣言文で明らかになったこと】
「要請文」「宣言文」の要求は単純で現館長の辞任要求である。しかし、2020年9月の「全療協ニュースを読んで」の時点では明らかでなかった事実が今回の文書で明らかになった。全療協の推す館長候補者が既にいたのである。宣言文には「後任には既に厚労省に伝えてある内田博文氏」と明記され要請書には「前任の課長が面談をすませている」とある。内田博文先生は全療協の有識者会議の座長であっていわば全療協の身内である。従って全療協は身内を資料館に送り込もうとしていることになる。内田先生は全療協が他組織である資料館館長の辞任要求や新館長を推挙することが筋の通らないことを承知した上で、厚労省課長と面談したのだろうか。内田先生にはそうしたことはありえないと思うのだが、なぜ全療協は「要請文」「宣言文」に内田先生の名を挙げ、「課長との面談」を実績として記載しているのだろうか。
ここまでが、「要請書」「宣言文」に現れた事実である。
【歴史的経緯の無視】
全療協は、資料館の人事に介入する大義名分を「当事者」という言葉を使い「資料館は全療協が作った」と主張する。しかし、くり返し述べるように資料館を作ったのは全療協ではなく国立移管を主導したのも全療協ではない。資料館の設立から国立移管まで、全療協は脇役に過ぎない。
歴史の修正は国であれ団体であれ、精神の堕落の第一歩である。
このことは、各方面から指摘され、また統一交渉団を飛び越えて全療協が単独で突出することの異常性も指摘されているから、繰り返さない。
【手続き上の疑義】
この正当性の全くない資料館への介入問題で、全療協は、2020年2021年と、二度にわたって規約を盾に「支部長会議」で多数決をもって反対意見を封じ込めている。しかし、全療協の歴史を見ると、建前上規約はあるものの、何よりも「団結」を最優先させ全会一致の運営を貫いてきた。分断を誘う「多数決」はいわば伝家の宝刀であって、長く封印してきた。東本願寺の「しんらん交流館」に「全療協の運動に終わりはない」(2020年2月6日)との寄稿で全療協の森和男会長自身「組織維持の基本は統一と団結」だと強調しているではないか。
歴史的に見ても、「予防法廃止」も2支部の同意が得られず廃止決議には至っていない。「国賠訴訟」も5支部の反対によって組織としては勝訴判決の直前まで支援の決定をしていない。この二つは現在全療協が運動の最大の獲得成果として掲げているものである。そのような重要な問題に際しても、「統一と団結」を第一にして拙速の決議をさけてきた。この原則を全療協の主要課題でもない「資料館問題」で放棄してしまうのはなぜか。しかもその経緯を見ると、課題として支部から上がってきたわけでも、十分な討議を経たわけでもなく、事務局長の主導で行われているのは明らかである。伝家の宝刀の抜きどきを誤ったとしか言いようがない。
【神事務局長・会長の遺訓】
流通経済大学の川崎愛氏による神美知宏会長へのインタビュー「全療協会長の『刀折れ矢尽きるまで』の闘い」(「社会学部論叢」2014年(25巻1号))が残されている。この中で神氏は「全療協が一部の人の運動になったら絶対成功しない」と強調している。この三年間の全療協の資料館の人事への介入は、会員である入所者の総意とも、支援者の支持を得た運動とも言えず、執行部の個人的関係に終始しまさに神氏の危惧通りになっているのではないか。とても神氏の「(全療協の動きを)相手(国は)はじっと見ている」と緊張しつつ「多くの市民各位のさらなるご支援を得ながら矢折れ刀尽きるまで闘い抜く」(2014年死の前日まで手を入れていたという「全療協緊急アピール」)という決意を継承するものとは言えない。
神さんに「罪」があるとすれば「僕がダメになったら全療協はおわり」(川崎、前掲論文)という強烈な自負のゆえに、後進の育成と全療協の精神と伝統の継承努力を怠ってきたことではないだろうか。
【蛇足】
ツッコミどころ満載の「要望書」「宣言文」だが、要請書に面白い一節がある。「この間、資料館運営が停滞し、資料館の評価は下がっています」。本当だろうか。コロナ以前は、入館者が機構改革以前を大きく上回り、コロナ禍の中でもリモート企画を次々と打ち出し、他の博物館からも活動を注目され、評価はうなぎのぼりなのが現実であって、評価を下げたいのは全療協の願望なのであろう。
また要望書と宣言文には「一体そこまで現館長にこだわる理由は何か。我々に説明がない」という一節があるが一読して逆に「全療協はなぜこれほど館長辞任にこだわるのか」という疑問を持つのは筆者だけではないだろう。
宣言文はこんな一節で締めくくられている。「(館長交代が)叶わなければ、全療協は今度こそ組織をあげて反対運動を繰り広げることを確認した」。このような恫喝めいた強がりといい、伝家の宝刀を抜き放ったことといい、今後、この軽率さによって全療協は鼎の軽重を問われることになるだろう。これもまた神前会長が最も警戒したことであり、このような政治的に幼稚な行動は神前会長のもとでは考えられなかったことである。
【大義なき宣言文】
以上のように全療協が他組織の人事に介入することに全く正当性がないことは明らかである。従って、内容的にも、手続き上からも、歴史的経緯からも、今回の「要請文」「宣言文」には大義はなく、このようなものを発出すること自体、輝かしい全療協運動に影を落とすものと言わざるを得ない。
全療協は否も応もなく終焉に向かいつつある。このような時、大義のない行動にうつつを抜かすのではなく、かつて全患協(全療協の前身)が「日患同盟(結核の患者運動)に運動のやり方を教わった」(川崎、前掲論文)ように貴重な運動の体験や教訓を、あとに続く患者運動や反差別運動に伝えていく責務があるのではなかろうか?
大義なき迷走する現執行部に直言する全療協関係者はいないのであろうか。
またこういう横紙破りを黙認することは、統一交渉団を有名無実化することになりかねず、交渉団としても一言あってしかるべきではないだろうか。