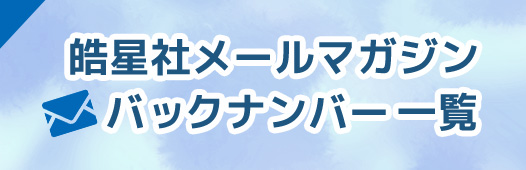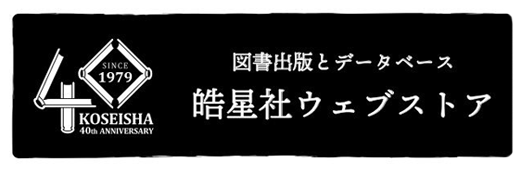この度のハンセン病資料館の元学芸員・稲葉上道氏たちの「不当解雇問題」につきまして
2020年8月17日
この度のハンセン病資料館の元学芸員・稲葉上道氏たちの「不当解雇問題」について私たちは以下のように考えます。
株式会社皓星社
代表取締役 藤巻修一(文責)
私たちは1979年の創業以来、ハンセン病患者、元患者さんたちの作品集の出版を手がけ、2003年から2010年にかけてはその集大成として『ハンセン病文学全集』(全10巻)を刊行いたしました。この企画がスタートしたのは1980年代に島比呂志さんの「自分たちの文学全集が欲しい」という新聞記事を見たのがきっかけでしたから30年以上前のことになります。その頃は、ハンセン病資料館もなく、長島愛生園では双見美智子さんが秋山正義さんの志を継いで、また多磨全生園では山下道輔さんが松本薫さんの意を受けて「入所者の資料は入所者が収集管理しなくては、将来ハンセン病の歴史は隔離を推し進めた国側の資料だけで書かれることになってしまう」という問題意識で資料の収集にあたっていました。それが神谷書庫でありハンセン病図書館です。私たちはその理念に強く共感していましたから高松宮記念ハンセン病資料館にも国立ハンセン病資料館にも違和感があって距離を置いてきたことも確かです。
国立ハンセン病資料館が始めて学芸員を採用した時、ベテランと新人をバランスよく採用すべきところ、新人ばかりを採用したのに一抹の不安を覚えましたが、その一人が稲葉上道氏でした。彼は、始めは恐る恐る、次第に大胆に最古参の先任学芸員として振舞うようになりました。その間、外部から見た資料館は、ミュージアムとしての基本である「収蔵目録」も作らず、『研究紀要』の発行もなく、啓発活動も外部への情報発信もなく何をしているかよくわからないというのが印象でした。資料を寄託しても収蔵庫に死蔵されるだけなので寄託をためらうという声も複数聞いています。それを許したのは、資料館の特殊な管理の構造だったと思っています。
国賠裁判勝利を受けて、高松宮ハンセン病資料館を国立に移管することを要請したのは原告団、弁護団(のちに全患協を加えて統一交渉団)でした。この時、資料館の内容に国が介入することを警戒し、干渉を排し人事の安定を求めていますから国立ハンセン病資料館の運営に統一交渉団は責任があります。しかし、厚労省、統一交渉団、受託団体が管理責任をめぐって三すくみ状態の中、稲葉氏の傍若無人な振る舞いを18年間も放置してしまいました。
近年、入所者の高齢化、減少に伴って資料館の存在意義は格段に増してきました。こうした時期、現場の職員から改革の動きが出たのは必然とも言えます。稲葉氏と他の職員との間に資料館や学芸員としてのあり方についての齟齬が表面化したのが今回の問題の本質であると考えます。稲葉氏がネグレクトを受けたとして「内部告発」を始め「組合を結成」したと同じ時期、「何をしているかわからなかった」ハンセン病資料館の活動は劇的に改善され啓発活動も活発化したのは客観的事実です。稲葉氏が主張する、復帰して資料館を「あるべき姿」に戻すというのが、稲葉氏が既得権を謳歌した改革以前の状態を意味するならば断固反対せざるを得ません。私たちは、この問題は現場の職員を中心とした改革運動であると考えますので、職員の行動を真摯に受けとめてあえて火中の栗を拾おうとした日本財団、笹川保健財団は、歴代の受託団体の中で初めて責任ある行動をとったものとして支持します。また逆に、統一交渉団を構成する三者のうち、全療協だけが突出して、内部に賛否を抱えているにも関わらず稲葉氏擁護のプロパガンダを行い自ら入所者の分断に与する理由が分かりません。
上述のように、問題は稲葉氏側が主張するような、「組合潰し」でも「不当解雇問題」でもなく、百歩譲って「労働問題」だとしても都の労働委員会に「救済」の申し立てをしているのですからその裁定を待つのが筋です。自己の保身のために、自然発生的ならまだしも自ら工作して自治会役員を賛同人に担ぎ、入所者に署名を促し、結果的に療養所内に分断をもたらすなどあってはならないことだと考えます。